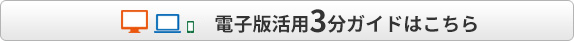- トップ
- 建設・住宅・生活ニュース
[ 建設・住宅・生活 ]

(2016/8/12 05:00)

開国まもない明治時代、主要航路に相次いで西洋式灯台が建設された。西洋の技術者の知恵を導入した灯台建設は日本の土木・建築技術のさきがけとなった。明治期に建設された灯台は120基で、64基が現存する。産業黎明期を照らした光をわれわれも追体験できる。
■夜間航行“停める”目印■
香川県坂出市にある鍋島灯台は、本州と四国をつなぐ瀬戸大橋が架かる与島から防波堤を渡った小さな島の上にある。周辺の海域は1日に約500隻の船舶が航行する。
点灯したのは1872年(明5)。英国人のリチャード・ヘンリー・ブラントンが設計した。高さ9.8メートル、水面から灯火までの高さが28.8メートルの石造灯台だ。一般的に灯台の明かりは白色だが、鍋島灯台は「不動赤緑互光」という赤と緑が交互に点灯する光り方。航路の分岐点を示す。
夜間航行を安全に導くことが灯台の役割だが、建設当初は船舶の停泊信号として使われていた。この...
(残り:60文字/本文:460文字)
(2016/8/12 05:00)
※このニュースの記事本文は、会員登録 することでご覧いただけます。